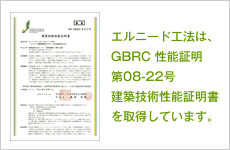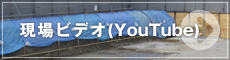1. 総則
スーパーラップル基礎工法における造成体は、ラップルコンクリートのコンクリートに変わるものであり、随時、求まった設計基準強度を必ず上回らなければならない。その為には、本仕様に基づく施工、施行管理、品質管理を確実に行わなければならない。そして、支持層の判別、混合の均質、セメント系固化材量及び水量そして土量、それらの確認と管理を確実に行わなければならない。
2. 施工計画書
- 施工業者は、工事に先立ちコンクリート工事の施工計画書を工事監理者に提出し承認を受ける。
- 施工計画書には、下記の事項について記載する。
(1) 施工手順 (2) 試験の種類(試験結果は、4.1~4に定める報告書を提出する。)
(イ)試料土の土質試験方法
(ロ)固化材配合試験方法(3) 施工基準
(イ)造成部仕様(計画)
(ロ)設計基準強度
(ハ)決定配合量
(ニ)使用材料名(4) 施工管理(品質)
(イ)溶液の配合管理の方法
(ロ)供試体による強度管理の方法
(ハ)施工記録の方法(5) 安全管理 (6) 組織体系 (7) 工程表(事前室内試験、試験結果報告書の提出、重機の搬入・搬出、試験改良などの時期) (8) その他必要と認めた事項
3. 材料
3.1 主材
建設現場発生土(砂質士、粘性土、シルト、ローム、有機質土等)
3.2 固化材
固化材は、特記による。特記の無い場合は、セメント系固化材、普通ポルトランドセメント、高炉セメントB種の中から事前室内配合試験を実施し決定する。
3.3 水
建設現場発生泥水(有機質を含まない)、あるいは、井戸、水道水。
4. 事前配合試験
配合量決定の為に工事着工に先立ち、下記の事項を必ず実施し、事前室内配合試験報告書として提出する。後工程及び安全を考慮し、材令7日における一軸圧縮試験結果が設計基準強度を上回った配合量を、決定配合量とする。
4.1 試料土採取
3.1の主材となる土を着工の10日以上前に採取し、下記の項目について試験する。
(1)自然含水比(配合量決定の際に添加水量を決定するため)
(2)湿潤密度(配合量決定の際に添加水量を決定するため)
(3)粒度組成(配合量決定の際に添加水量を決定するため)
4.2 試験練り
- 固化材特性関係式を用い、必要設計基準強度を満たす各配合量を求める。
(σ7式)
log qu=2.462・log a-1.944・log w-1.586
qu:一軸圧縮強度(kg/cm2)
qu=k・Fc(k:現場測定値qu'/Fc)
a:固化材量(kg)
w:調整含水比(%)
w=∑W/ms ×100
∑W=mw+wl+w2
w1:スラリー溶液水量
w2:調整水量
mw:土の自然含水比
ms:土の乾燥重量 - 所定量の土と固化材と少量の水をソイルミキサーに入れ混合を始める。
- 造成体特性を観察し、フロー値による計測を行い適正添加水量を決定する。通常は8.5cm~13.0cmの範囲とする。
- 混合完了後、直ちにモールドに充填後湿空養生にて保管する。
4.3 圧縮試験
- 供試体の圧縮試験方法は、JIS A 1108による。
4.4 圧縮試報告書
- 試料土の土質試験結果として、自然含水比、湿潤密度、粒度組成の報告を行う。
- 固化材配合試験結果として
(1)適正フロー値の計測結果の報告を行う。
(2)試験練り配合量の報告を行う。
(3)各供試体の圧縮試験結果報告を行う。
(4)決定配合量と決定フロー値の報告を行う。
5. 施工
施工業者は、工事監理者と綿密な打ち合わせの基に工事に着手する。
施工中は、特に品質管理に関わることには細心の注意を払う。
- 着工前・着工中・工事完了後の確認事項に関する詳細は、別途に定める「現場管理者マニュアル」による。
- 施工に関する具体的な注意事項及び管理事項は、別途に定める「現場管理者ハンドブック」による。
6. 品質管理
「現場管理者ハンドブック」に詳細は記載されているが、必ず守らねばならない。事項について下記に記載する。
| (1) | 設計計画書に基づく支持層の確認。
|
||||||||||||
| (2) | 決定配合量に基づく混合を行うために
|
||||||||||||
| (3) | 均一混合を行うために
|
7. 強度管理
工場生産のコンクリートと違い、建設現場発生土を主材料とするため造成体単体の中でのバラツキも把握し、合格判定強度を確実に上回る事を確認しなければならない。その方法としては、現場状況を考慮し下記2種類の試験方法の内、いずれかの方法を用いる。
造成体厚さが4.0mを超える箇所は(1)(2)を併用する。
(1) 塩ビのパイプ(φ100mm)を造成完了直後に造成体に差し込みコアを採取する。初期硬化発現後パイプを引き抜き、所定供試体サイズに成型する。 (2) 造成完了直後に造成体の一部(深度方向中間部~下部)を直接採取し、モールド管6本に充填する。 - コア採取は、コンクリートの採取基準に準じ、総造成体積150m³に対し、1箇所以上とし1箇所当たり挿入する塩ビ管は1~3本とし、ランダムサンプリングにより合計6個以上の供試体を作成する。
- 供試体は湿空養生後、材令7日及び材令28日の一軸圧縮試験を実施する。
- 日本建築センターの「建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指指針」による検査手法Aにて合格判定を行う。
8. 施工報告書
- 工事終了後速やかに、施工報告書を作成し、工事管理者に提出する。
その際、次項目を記載すると供に施工工程写真と材料搬入写真とを添付する。 - 施工報告書には、下記事項を記載する。
(1) 施工基準
(イ) 造成部仕様(計画) (ロ) 設計基準強度 (ハ) 決定配合量 (ニ) 使用材料名 (2) 施工管理(品質)
(イ) 溶液の配合管理の方法 (ロ) 供試体による強度管理の方法 (ハ) 施工記録
日付、図面no、造成幅、掘削深さ、造成厚さ、造成体積、使用固化材量、フロー値、供試体採取有無(3) 安全管理 (4) 組織体系 (5) 工程表(事前室内試験、試験結果報告書の提出、重機の搬入・搬出、試験改良などの時期) (6) その他必要と認めた事項
有限会社ネオニード 香川県高松市屋島西町2485-21 TEL(087)841-0161 FAX(087)841-8759
© NEO-Knead, Inc.